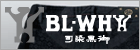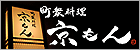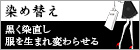京黒紋付染ができるまで
染めの行程
 1. 白生地検反・墨うち
1. 白生地検反・墨うち
白生地段階で織難や汚れがないか検反します。
合格した白生地のみ墨うち(袖や身頃といった着物の各部分の決定)を行います。
 2. 紋糊置き
2. 紋糊置き
家紋部分の防染糊置き。
墨うちで決定された袖紋、胸紋、背紋に紋糊を置いていきます。
紋糊には色々な型があり、 また、男紋と女紋では大きさも違います。
 3. 染色行程
3. 染色行程
下染め後、京黒紋付染め独特の継続染色で染めていきます。
 4. :紋糊落し
4. :紋糊落し
前述の紋糊を落していきます。
熟練を要す工程です。
 5. 中間検品
5. 中間検品
深色工程前に検品を行い、品質の向上に努めます。
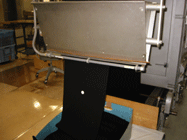 6. 濃色(深色)加工
6. 濃色(深色)加工
中間検品に合格した商品を濃色、深色加工します。
濃色加工技術の向上に伴い、より深みのある黒が生まれました。

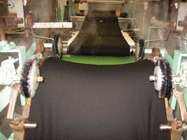 7. 湯のし(ピンテンター)
7. 湯のし(ピンテンター)
生地巾を整えて巻き取り、ピンキングしていきます。
 8. 紋洗い
8. 紋洗い
紋を白く漂白します。
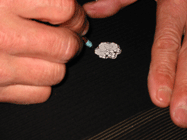 9. 上絵
9. 上絵
伝統工芸士により紋を書きます。
家紋は現在約2万種類あるといわれています。
一般的な平安紋鑑では約4千種類の紋が掲載されています